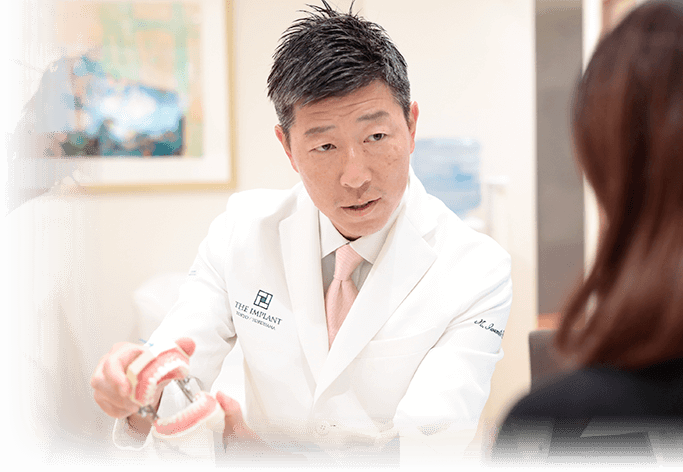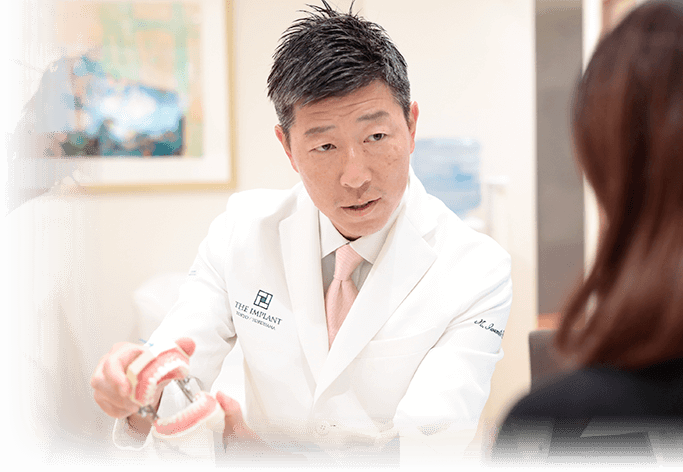死因の「第3位」、脳梗塞は歯周病が引き起こす?
厚生労働省による最新の「人口動態統計の概況」によると、2017年の1年間で10万9,880人の方がいわゆる「脳血管疾患」で亡くなっています。
これは死亡者全体の8.2%を占め、死因別の順位では「悪性新生物(ガン)」の27.9%、「心疾患」の15.3%に次ぐ第3位と、日本人にとっての“死因ワースト3”の一角をなす恐ろしい病気だといえるでしょう。
この怖い「脳血管疾患」のうち、最も死亡者数の多いのが6万人以上を数える「脳梗塞」で、これは「脳内出血」の3万人あまりや「くも膜下出血」の1万人あまりを大きく上回るとともに、年々その数が増えているのが不気味なところ。
そして、歯科医である私としては、こうした傾向はじつのところ高齢者における歯周病の増加と大きな関係がある……そういわざるを得ないのです。
/BFDB2936-34F5-4315-B2BB-D592E36F250D.jpeg?width=600&name=BFDB2936-34F5-4315-B2BB-D592E36F250D.jpeg)
(出典)厚生労働省「平成29年人口動態調査」
前に別のブログで書いたように、歯周病などで歯を失うことは必要な栄養をきちんと取れず、ゆっくりと、しかし確実に死へと向かって進む結果につながります。
しかし、実際のところ、それ以上に恐ろしいのは歯周病がよりダイレクトに、患者さんの生命を奪う根本的な要因になるという事実です。
なかでも、ここであげる「脳血管障害」、とりわけ最も恐ろしい「脳梗塞」は歯周病がその直接のリスクで発症することを、ほとんどの方がご存じありません。
“サイレント・キラー”と戦うために「歯科ドック」を!
「脳梗塞」という病気は、脳内を網の目のように走る血管の一部が何らかの理由で詰まって、血流がストップし、それによって脳の細胞が死滅することで発症します。
原因としては、加齢により血管の弾力が失われたり、心房細動といって心臓の動きが不規則になって血管の中に血栓(血の固まり)ができるなど、いろいろですが、歯周病と深いかかわりがあると考えられるのが「アテローム性動脈硬化」という、血管の内側の壁が狭くなる症状です。
アテローム(正式にはアテローム性プラークといいます)というのは血管の中でコレステロールがお粥のように固まる状態のことで、それが内側の壁に付着すると血液の流れが悪くなり、血栓ができて、最悪の場合には血流がストップしてしまいます。
こうして起こる脳梗塞のことを「アテローム血栓性脳梗塞」といい、脳の血管のなかでも特に太い箇所に起こりやすいため、脳の広範囲がダメージを受け、そのまま死亡したり、仮に助かっても寝たきりになる可能性が高くなるのです。
血管の内側にできるアテローム性プラークは、これまで高血圧や糖尿病、脂質代謝の異常などがその大きな原因といわれてきました。
ところが、最新の歯科学研究の成果によると、その発生に歯周病が大きくかかわっているというのですから、歯科医としては見過ごしにはできません。
具体的なメカニズムとしては、歯と歯茎周辺の毛細血管を通じて歯周病菌が血管内に侵入し、増殖した細菌が出す病原因子や、炎症にともなってつくられるサイトカインという物質がアテローム性プラークの形成を加速――結果、脳梗塞の発症リスクが大きく高まると考えられています。
このように、歯周病はたんに歯の病気というだけでなく、患者さん本人がまったく気づかぬうちに、じわじわと命をむしばむ恐るべき“サイレント・キラー”です。
最近は、脳梗塞や脳内出血を予防するために「脳ドック」を受ける方が増えており、それによって症状のあらわれないごく小さな脳梗塞が見つかることも少なくありません。
脳の細い血管がつまることで起こる、こうした軽度の脳梗塞は「ラクナ梗塞」と呼ばれますが、これが見つかるということは、近い将来により大きな脳梗塞が起こる前兆とも考えられるでしょう。
そうであれば、考えられるリスクを少しでも抑えておくことが、何より急がれるはず。
そのためにも、脳梗塞をはじめ生命の危機を招く恐れのある病気、その根本原因になる歯科疾患をチェックすることが重要になります。
私どもが定期的な「歯科ドック」を受けるようおすすめするのも、こうした深い理由があるからにほかなりません。
ご自分の歯の健康を守ること、それはそのまま大切な命を守ることにつながるのです。