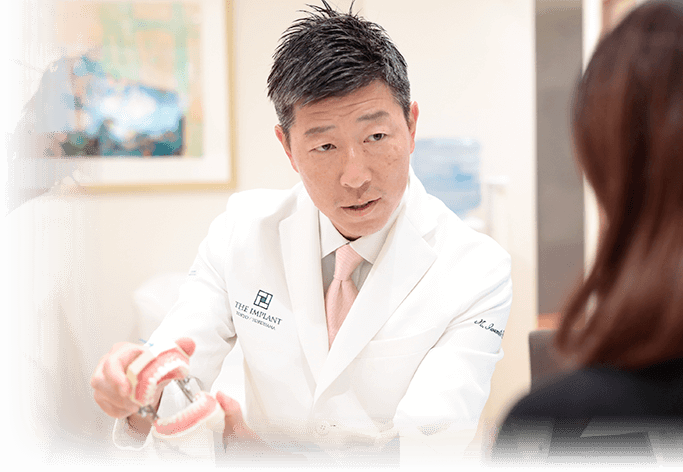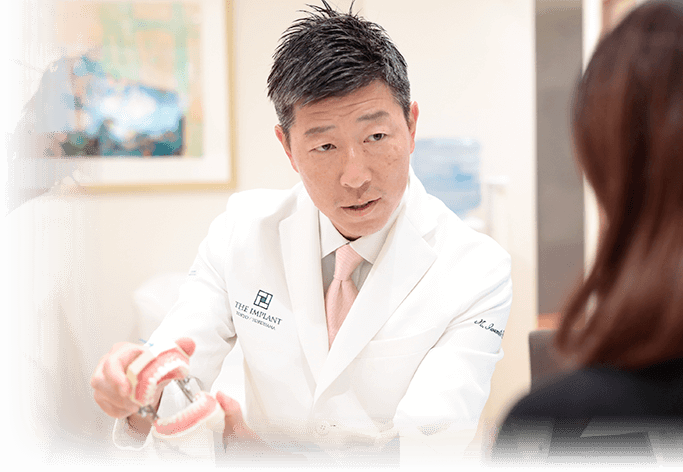歯を長く守っていくために必要な“知識”と“スキル”を身につける
私どもでは「歯科(予防)メンテナンス」を、ひとつの診療科目としてあつかっています。
歯科におけるメンテナンスというと、歯科衛生士が患者さんの歯垢(プラーク)をきれいにしてくれるなどのケアをご想像になる方が多いのですが、私どもの
歯科(予防)メンテナンスはそれとはまったく違う発想に基づくものです。
すなわち――
メンテナンスを行うのは基本的に患者さんご自身、スタッフはそのためのアドバイスやお手伝いをさせていただくためにご一緒する
――それが、私どものメンテナンスに対するスタンスであり、
患者さん自らがご自分の歯を長く守っていけるようご指導し、必要な“知識”と“スキル”を身につけていただいています。
私の見るところ、日本では歯の健康に関する正しい教育が不足しており、歯ブラシを使っての磨き方ひとつとっても、ほとんどすべての患者さんが我流で行い、どこを、どのように磨けば効果的に歯垢を除去できるかさえ、おわかりではありません。
これでは、たとえ歯科医での治療を受けてもいたちごっこで、歯周病や齲歯(虫歯)が何度となく再発してしまうのは当然の話でしょう。
そうした悪循環を断ち切り、ご自分の歯をいつまでも守り続けるため、スタッフがそばに付き添ってお手伝いをするというのが、
私どもの考える「歯科(予防)メンテナンス」です。
メンテナンスの第1段階は初診の際、歯周病菌の温床である歯垢がどれくらいあるか、プラークチェッカーという染色液で染め出し、患者さんの目で確かめていただくところから始まります。


歯周病の原因菌は、当然ながら肉眼で見ることができませんが、ピンク色に染まった歯をじかにご覧いただけば一目瞭然です。ご自分の歯が、どれほど大量の歯周病菌にさらされているかに驚かれたところで、スタッフがこれを歯ブラシできちんと除去するための磨き方をお教えし、その場で患者さんに体験していただきます。
この、正しいブラッシングのスキルこそメンテナンスのための基本のキであり、立方体をした歯の5つの面を28本きちんと磨くことで、プラークの量を歯周病が発症しないレベル(16%以下)に抑える――そのためにも、患者さん自らが正しい歯磨きのやり方を体で覚えることが何より重要なのです。
この段階ではまた、歯周病が発生するのはなぜなのか? 原因とメカニズムについて詳しくお話し、正しい知識もしっかり身につけていただきます。
あまり知られていませんが、歯周病というのは文字どおりの「生活習慣病」であり、歯そのものはもちろん、体全体の健康や抵抗力を高めることが発症のリスクを減らすうえで不可欠です。
そのために、食生活をはじめとする生活習慣について詳しくお聞きし、それに基づいて患者さんおひとりおひとりに必要な日常の注意点をご指導しています。
こうして、歯の健康を守るためのスキルと知識を身につけていただくのと並行し、歯周病や虫歯の処置、あるいは矯正やインプラントなど必要な治療が行われるわけですが、それが終わればもう大丈夫、というわけにはいきません。
せっかくとり戻した歯の健康をこれからも維持し続け、二度と歯を失うことがないよう、再発防止のためのプログラムを正しく行っていく必要があります。
ここからが、いよいよ歯科(予防)メンテナンスの第2段階の始まりです。
具体的には、治療によって新たにできた咬み合わせ、インプラントで入れた人工の歯のかたちや素材の特性、さらには残った自前の歯も含めた、患者さんそれぞれの新しい口内環境に合わせたメンテナンスを指導。
歯垢のたまりやすい箇所、磨き残しの出やすい箇所はどこか? これをきちんと除去するには、どのような点に気をつけてブラッシングをするべきか? 食生活や習慣上の注意点は? などなど、引き続き患者さんと二人三脚で歯の健康をお守りするべく、専任の担当者が定期的なチェックアップをいたします。
歯科(予防)メンテナンスとは、スタッフまかせのプラークコントロールではなく、患者さんご自身がご自分の歯を守ること。
私どもではその考え方に立って、ご信頼のうえに長くお付き合いをさせていただけるよう、日々心がけてまいります。